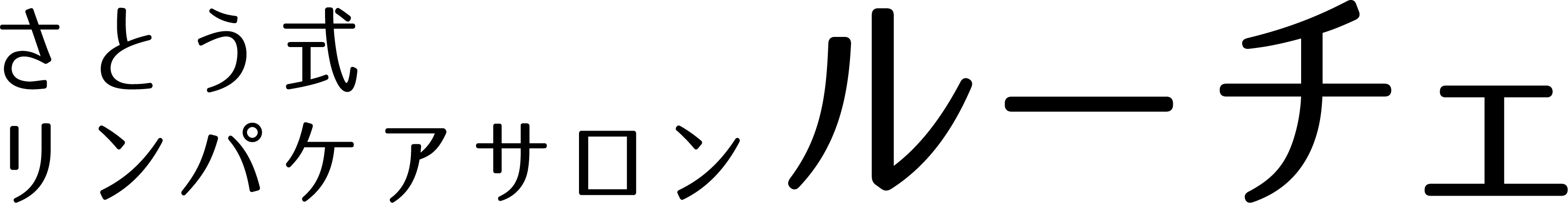🍶 手作り味噌の会
立冬を迎え、
そろそろ、お味噌の仕込みにぴったりの季節になってきました。

頑張りすぎず、自分を大切に
ココロとカラダを整えるお手伝いをしています。
心・気・体、生きる力のサポーター
稲葉起久代です。🌱
🍶お味噌の寒仕込みの季節🍶
寒い時期に仕込む「寒仕込み」は、
ゆっくりと発酵が進み、
旨味やコクが深まるお味噌に育っていきます。
自然の寒さが、
余計な雑菌の繁殖を抑えてくれるので、
初めての方でも失敗が少なく、
安心してお味噌を仕込むことができます。
季節の流れとともに、
少しずつ熟していく手作りのお味噌──
そんな自然のリズムに寄り添った、
昔ながらの知恵が「寒仕込み」です。
そして、この日は、
年に数回、お客様のリクエストで開催をする
「手作り味噌の会」
初めてのお味噌づくりはコロナ禍の直前。
以来、
お味噌づくりは、100組以上の皆さんとご一緒しているのですが、
この日は、「家族が美味しい😋って言ってくれるから」と、
グループで続けてくださっている皆さんと
お味噌づくりをしました。
もう何度も仕込みをしているので、
今ではみなさんサクサクと作業が進みます😊
※ 大量の材料調達は、麹屋さんの助けを借りて準備をします。
ちなみにですが、
🫘 生大豆から作るお味噌づくりをご紹介いたします
(以前は、私もこんな風に「お味噌づくり」をしていました。)
1.生大豆を一晩浸水

2.浸水した大豆を丁寧に灰汁を取りながら茹でる
(お鍋で6時間ほど。指でつぶれるくらいが目安)

3.麹をほぐす

4.塩きりをする(塩と麹をよく混ぜ合わせる)
※「塩きり」をしっかり行うと、美味しく仕上がります

5.茹で上がった大豆を潰し、耳たぶくらいの柔らかさに調整


※ 袋の中でまとめてつぶすorマッシャーやすりこ木でつぶす(お好みで・・・)
6.大豆の粗熱が取れたら、塩きりした麹を混ぜ合わせる

7.よく混ざったら味噌玉を作る

8.空気を抜きながら保存容器に詰める
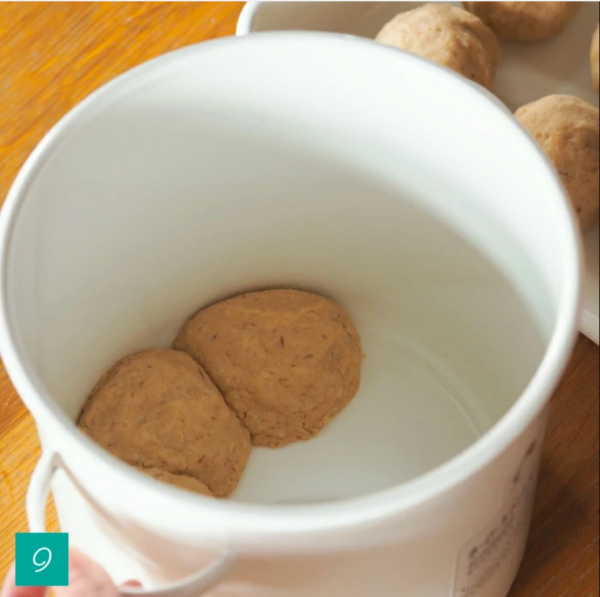
9.表面をラップで覆い、カビ防止にワサビをのせる
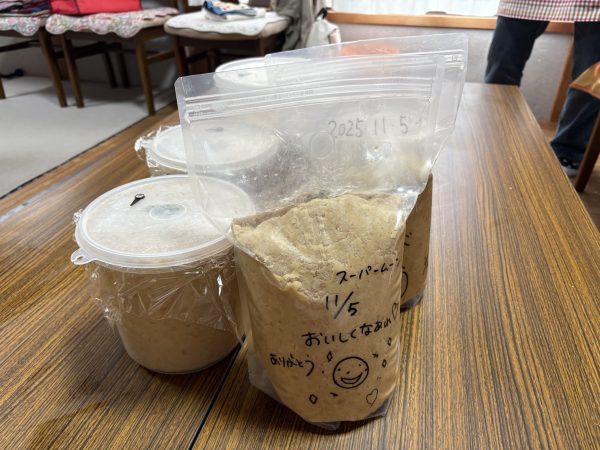
👉 約2〜2ヶ月半から召し上がれます。
(仕込みの時期や保存場所によって前後します)
🔵 発酵が「浅い」お味噌は、麹の香りが良く
🔴 熟成の進んだお味噌は、うま味成分マシマシ
「どのタイミングでいただくか?」も、味変を楽しめます。
コレも、麴菌の生きている「手作り味噌」ならではの味わいです。
※ 万が一、熟成中にカビが生えてしまっても、
カビの部分とカビ周辺を取り除いてあげれば
召し上がっていただいても大丈夫です。(自己責任でお願いします。)
本来は、生大豆から仕上げてこその“手作り味噌”ですが、
浸水から完成まで二日がかり。
今では、何十キロもの味噌を仕込むようになったので、
材料の調達から大豆の下ごしらえは麹屋さんにお願いして、
「混ぜるだけ」のお味噌づくりを楽しんでいます。

そんなの、「手作り味噌」じゃないじゃん・・・💦
確かにそうです。
🌿 それでも、手作りにこだわる理由は、
1,素材が分かるから安心
大豆:北海道産「とよまさり」
麹:静岡県産「愛知のかおり」
塩:静岡「あらしお」
2,添加物が入らない
市販の常温味噌には、発酵を止める「酒精」などが入っていることがあります。
3,熟成の期間によって「味変」が楽しめる
熟成の短いお味噌は麹の香りが高く、長いお味噌は味噌の味わいが深い
4,そして、何より美味しい!
決して「完璧」ではないけれど、
ゆる〜く続ける“食の養生”。
頑張らないから続けられる
素材と手作りにちょっとだけこだわったお味噌づくり、
ご一緒しませんか?🤎
これから寒さに向かう、12月、1月、2月は
手作り味噌の仕込みの「旬」
年明けには静岡での開催を計画中
日程はinstagramにて、お知らせをしますので
よろしかったらフォローをしてくださいね💕
気になる方は、お気軽にお問い合わせくださいね。
instagramのフォロー
※ instagramからもお問い合わせいただけます。
最後まで、読んでいただきありがとうございます。
あなたの日々が、あたたかく巡っていきますように